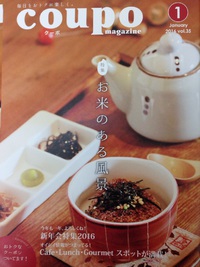2012年09月03日
9月。
エイサー
おはようございます。
旧盆ウークイ、あちこち渋滞なども大変だったようでしたが
みなさん疲れは残ってませんか?
お盆ならでは、の道ジュネーを満喫された方も多いことでしょう^^
あの太鼓の腹に響くような感じが好きです。
さて、9月に入りました。
明日に「おにぎりマイスター認定講座:3期生」の講座が
スタートします。
で!!

マイふりかけを1期生から持ち込んでたのですが
人気なのがコレでした♪
しかし・・・
ごめんなさい、2期生のみなさんの時に切らしてしまい
しかも
購入したお店を覚えてないという状態で(涙)
申し訳なく思っています。。
(もしブログ見てたら「丸大(牧港店)」にもありましたっ)
ついで買い
↓

雑穀が混ざっているふりかけ、も意外と面白いという反応です

どんな方々に出会えるのか
また楽しみです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(exciteコネタより)
面白い行事発見♪
時期も関係ないのですが
年末・年始まで待てない・・性格なので
「ふ~ん」という感じで読んでくださいませ(▽//;)

お米レシピ
白いご飯をおいしく食べるためのレシピ、お米レシピ
青森県にはちょっとかわった伝統行事がある。「おこもり」と呼ばれていて
年末と年明けの2回(12月15日と1月15日)行なわれるものだが、
子供からお年寄りまで神社にこもってご飯や汁を食べまくるというものなのだ。
この行事は下北半島の西側にある青森県佐井村で行われている。
神社に集まった人々は、はしでおわんをたたきながら「めしーっ」「しるーっ」
と奇声を張り上げ、ただただ食べまくる。「おこもり」は江戸時代から続く
伝統行事で、漁を妨げる鯨を退散させるために始めたのが起源ともいわれている。
白いご飯に、豆腐とキノコのすまし汁、ゼンマイのあえもの、たくあん、
というのが定番。
この佐井村の他にもお米をたっぷり食べるという地域がある。
石川県の輪島市久手川町に伝わる「もっそう祭り」。こちらは約五合のご飯が
高く盛り上げられたものを先人の苦労をしのびながら食べるというもので、
毎年2月に行なわれている。
「もっそう」は円筒形の木の枠で、約五合のご飯をこの枠につめておわんに
もって食べることからこの名がついた。そして、何故先人の苦労かというと、
この祭りはもともとは藩政時代の厳しい年貢の取り立てに、隠し田で作った米を
役人の目を盗んで食べたのが始まりとされているからなのだ。こちらの方は
「おこもり」とは違ってちょっとお上品。お椀に盛られた五合のご飯はさすがに
食べきることは難しいので祭りの後は各自重箱に入れて持ち帰るのだそうだ。
やっぱり日本人とお米はきっても切り離せないものなのだなぁ。これ以外にも
全国各地にはお米食べまくりの風習があるのかも。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
沖縄の県産米を皮切りに
日本全国のお米の新米シーズンとなります。
8月出た鹿児島・宮崎のこしひかり、
それから関東方面へ北上していくのですが
9月後半から10月にかけて、九州でも晩稲な品種が
待っています

Posted by こめなな at 08:08│Comments(0)
│おこめ
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。