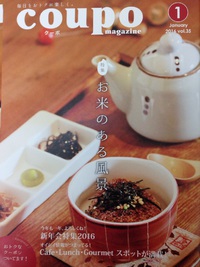2013年01月05日
もち♪ モチ♪ 餅♪

もちつき。
この時期の定番イベントですよね~(笑)。
昔、おもちは特別なときだけに食べる「ハレの日」の
食べ物でした。
今でも、お正月に神仏に供える「鏡もち」、
子供の健康や子孫繁栄を祈る桃の節句の「菱もち」や
端午の節句の「柏もち」、鶴の卵の形でお祝い事に使われる
「つるのこもち」などに、その伝統は継承されています。
( ↓ 「つるのこもちって・・どんなん?」と思った方へ)

おはようございます。
今日も冷えますね~、しばらく続きそうな寒さです。
そんな中でも、ちらちらと桜が花開き始めています。
もう「春」になるんですね。
ぐっと冷えるのと、少し暖な日が交互にくると
更に見頃に近づくはずです

さて。
個人的にすごく「餅」が幼い頃から大好きな私。
小学校の頃、13祝いの年(5年生)になると
上級生(6年生)が臼と杵で餅をついてあげるのが恒例行事でした。
その時のきな粉をまぶした、粒感の残ったお餅の味を
忘れることができません

最近ではパックにされた切り餅などがあり、手軽に楽しめるように
なっていますが、臼と杵でつく餅はまた格別ではありませんか?
「蒸したもち米、扱ってませんか?」
という問い合わせも米屋をしてるとけっこうあるものです。
炊飯事業が伸びていくのも、なんだか分かる気がしました。。
公民館などでもちつき大会などが行われる地域はまだ多いのですが
では?
どんなものが必要で、何を準備したら良いのでしょう

【道具と材料】
・臼と杵(最近はレンタルもあります)
・蒸し器
・もち米(少なくとも一升:約1.5kg、用意します)
・もちとり粉(上新粉、片栗粉など。もちがくっつかないように全体にまぶす用)
【前日の準備】
・もち米は前日に洗い、たっぷりの水に一晩tけておきます。
・臼には水を張り、杵は水に浸しておきます。
【もち米を炊く】
・もち米は蒸す一時間くらい前にざるに上げて水をきり、強火で蒸し上げます。
指でつぶして芯が残っていなければOKです。
【もちをつく】
・蒸しあがったもち米を臼にあけ、杵でもち米を臼の縁に押し付けながら
米の粒がほぼつぶれるくらいまでこねます。
(柄をしっかり持ち、体重をかけてこねます)
・杵でつきます。
もちがくっつかないよう、ときどきお湯で湿らせます。
(振り下ろすときは最初だけ力を入れ、あとは杵の重さを利用して搗きます)
・もちを搗く合間の「返し手」は手をぬるま湯で湿らせながら
もちを中心に向かって折りたたむように返します。
米粒がなくなって、なめらかになったら搗きあがり。
まぁ・・・実際に搗いてみないとわからないカンジですね(▽//;)
臼と杵で搗くおもちの味は格別♪
ただ、準備も大変そうだし、量もハンパない気がする・・・
気軽に楽しみたいときには
炊飯器を使ってみましょ。
搗いたもちにはかないませんが、欲しい量だけ作れます^^
もち米は蒸す代わりに炊飯器で炊きます。
水加減は米と同量にするのがポイント。
炊き上がったらすぐにボウルに移し、すりこ木でよく
搗きます。
米粒が見えなくなり、なめらかになったら出来上がり。
『米』は気を補充する基本食材。
もち米も疲労回復時のお助け食材♪
気を補うとともに、目減りを防ぐ「気のダダ漏れストッパー」な
食材。
新年を迎えてすでに少々お疲れ気味・・・という方へ。
「気が不足した状態=気虚」
気は全身のいたるところを流れている目には見えないエネルギー。
元気・やる気・本気・気分がよい・気が合う・気を遣うetc・・
生命活動を維持するエネルギー源である気が不足すると、
常に倦怠感や疲労感があり、新陳代謝も悪くなるので美容にも
影響してきます~。
風邪をひきやすい・胃の調子がすぐ悪くなる・朝なかなか起きられない・
声が小さい・汗かき・生理が長い・・・というのに思い当たる方は注意を。
それらが特徴としてあるようです。
「趣味ですか?」というほどに慢性化してしまわないように
改善していきましょう。
ただ、『頑張るぞ~』と気負わないように。。ね^^
Posted by こめなな at 08:53│Comments(0)
│おこめ
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。