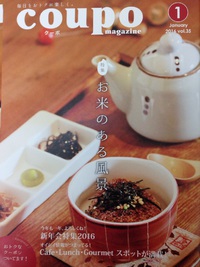2013年02月23日
『あたりまえ』

実は大好きな「くまもん」。
画像見てると、こういうの見つけました。。。
こんな風に並んで座っているくまもんを見てると
不思議な感じではありますが、やっぱり大好きです(▽//)♪
おはようございます。
おだやかで気持ちの良い朝ですね。
週末、東北地方などでは史上最大級の寒波が流れてくるなどと
なんだかすごい状態なようですが、これを過ぎるとようやく
春に向かうというお天気ニュースがありました。
機会があれば、ぜひ本土の桜を見たいと願う今日この頃です。
(私、実は雪と桜は見たことがなくて
 )
)幸運にもいろいろな学びの場をいただくことが多いのですが、
これまではコミュニケーションであったり、どちらかというと
自己啓発系でした。
今。
素直に「食」関係での機会が多くなりました。
たぶん、自分の中でも方向性というか、何を深めていくのかを
決めたカンジでしょうね(笑)。
最近キーワードでよく浮かぶのが
「あたりまえ」
・・・あたりまえ体操も好きではありますが(▽//;)
ではなくて。
あなたにとって、健康とは何ですか?
ことあるごとにこう質問しているウザ絡みちうな私ですが
ある方が素敵なことを言いました。
「幸せ」と、つぶやいたあとに
「あたりまえにあって普段は見えない大切なもの」
まさにそうなんですよね。
これは健康だけにいえることではなく
今現在私達が置かれている状況や普段の生活の中で
共通することだと思います。
お米の講座も、そのあたりまえにそばにありすぎて
実はその良さも置いてけぼりになっていた部分を気づいて
欲しいという想いのもとに始めました。
より良くを求めることは、すごく自然なことですが、
便利性・機能性だけを求めていくと
大事な部分がすこ~んと抜けてしまうんですね。
そうするとどうなるのか。
食の及ぼす影響は、身体や心にもつながるわけです。
食の多様性は農業や産業など、小さなほころびから大きくもつれるように
いろんなものに影響している気がしてなりません。
興味深い記事を見つけました。
「食べない日本人の時代」と称されていた記事で
~安すぎる食が農業脅かす~とな。
全国農業経営者研究大会・経営戦略分科会で
(株)グッドテーブルズ代表の山本謙治氏
氏は農産物流通コンサルタントで脳性・食生活ジャーナリストとしても活躍
「やまけんの出張食い倒れ日記」
↓ ↓ ↓
日本の食は安すぎる。
安すぎるからいろんな問題が生じてくる、と主張。
一般紙からどのぐらいの価格なら適正なのかを書いて欲しいと言われたコラムで
「消費者が食品の安全性を本当に担保したいと思うのなら
価格を2倍にする法律を作る。
その価格上昇分を小売が持っていかないよう価格のトレサシステムを作り
上前が中間流通、生産者団体、生産者にも適正に割り振られるよう食糧価格安定法
みたいなものをつくればいい。
スーパーからこの価格で特売やるから納品しろ、と言われても普通のコスト構造では無理。
食品メーカーが偽装してしまうのもここに原因がある。
適正利益の取れるちゃんとした価格なら偽装は起こらない。」
できるだけ安い値段で、と消費者の見方をするのがもっとも当たり障りのなく
轟々たる非難がくるのも覚悟していたが、必ずしもそうではなかった。
日本の農産物や食品が安いのを補填するのが補助金だったりするが、
ここは世論として逆風が吹いている。世論を変えていくには声を上げ続けるしかない
が、一般の消費者にはあまり届いていない。そこをどうするべきかについても話していきたい。
まず日本の食の現状とトレンドをみていきたい。
食糧消費は右肩上がりではない。
たくさん食べる時代は終わっている。
国内食糧支出額は1995年がピーク。
成人1人あたりのカロリー摂取量は多いときは2020カロリーあったが
最近では1860キロカロリーにおちている。
これは大正時代のころとほぼ同じ。
いまの日本人は食べ物は豊富にあるのに
「選択的に食べなくなった」といえる。
食のマーケットは、人口が確実に減っていく。
将来人口の推計値はいろいろあるが、2050年に1億人を割り込む
点では一致している。
それだけ胃袋の数が減ることになる。
すでに高齢「化」ではなく、「高齢社会」に入っており、
1人当たりが食べる量も少ない。ここ15年ぐらいで若者たちの質も
変わってきており、内向的であまり食べないし(酒を)、飲まない。
食の市場について最も影響が大きいと思うのが世帯の縮小。
「1世帯が何人で構成されているか」だ。
貞和40年代は1世帯人数が少ないというイメージで「核家族化」の
進行が叫ばれていた。
いまは単身世帯が圧倒的に多い。東京都だけでみると65%ぐらいが
単身者世帯だ。単身、もしくは2人世帯では、葉野菜なら1玉はいらない。
大根も1本は不要だ。
いまの40歳以下の世帯は継続的に食材を使っていくことをしない。
余った食材を翌日以降も別の料理で活用していく発想ができないし、
ない。理由は料理のレシピが頭に入っていないからだ。
料理技術をまともにもっていない男女が多い。
要は母親からそれを教わっていないのだ。
料理ができない人は、自分の家に必要最低限のものしか買いたがらない。
皆が最適買いをすればするほど売れる野菜の量は減っていく。
これはコメについても同じだ。
だから世帯が縮小すていくのは深刻な話なのだ。
消費者の考えも変わってくる。
かつては皆がある程度は似たような幸福感や夢を持っていたが
バブルがはじけてからは階層社会になった。
一部の金持ちはいるが、中位・下位は何分割にも細分化された。
以前はわずかしかなかった清涼飲料水もコンビニにいけば分かるように
何十種類も並んでいる。
農産物みたいに細かなニーズに応じて作り分けられないものは
売れにくくなっている。
料理ができない消費者は当然、外食・中食に流れ込む。
外食・中食チェーンだと食材コストを抑える必要があり
国内産の農産物は高くて買えない。昨年、西友が中国産米を販売したが
これもよく売れた。
実際、私も試食をし国内産よりは味が劣る幹事だったが
知り合いの大手米屋さんによると、それを飲食店が買い、
国内産のコメと混ぜて使ったとのこと。
食べる側の人たちがちゃんとした舌を持っていない。
日本では良質な農産物や食べ物を作っても、どこが良質なのかを分かってもらえない
危機に直面しつつある。
農村でも食文化の伝承は危うい。
愛媛大学の友人が愛知と愛媛の専業農家を調査したところ
約7割はパン食。漬物などの郷土食も伝承されなくなってきているという。
専業農家の問題はやはり婿や嫁。
運良く嫁をもらうと、同居もせずに別宅を建てる。
ここでかまどが分かれるから郷土料理が伝承されなくなるのは分かると思う。
しかし、自体はこれだけにはとどまらない。
都心部からきた嫁が洋食ばかり作り、そこに親達も呼ばれる。
そのため祖父母世代も洋食化していくようだ。
実際、地方の人たちは郷土食には飽きてきているケースも多いので
このことはよく分かるきがしている。
お米。 ごはん。
いろんな研究がなされていて
いろんな結果が報告されているのは
喜ばしいことです。
私自身も米やごはんのお話から食育へ繋げるので
今流行的な玄米などももう少し深める必要を感じています。
玄米だけなく、それ以前の稲や品種改良について
学ぶ場もいただいています。
でも
もっと「普段着」な存在であってほしい。
これに着替えるとほっと落ち着くような
そんな存在の「米」であってほしい。
きっと、大切なものはもっと単純なこと。
ただ、今はまだその辺がアバウトなので
みなさんにきちんとお伝えすることができないのですが
そのために、まだまだ進んでみますね~♪
今週末、東京マラソンらしいです。
走る、のはもっぱら苦手なので専門外ですが。
それよりも、私的には日曜に開催される
お米マイスター全国ネットワーク会議に参加したかったなぁ

という部分で、少しふつふつとしてるこめななでした。。
Posted by こめなな at 09:47│Comments(0)
│食育
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。