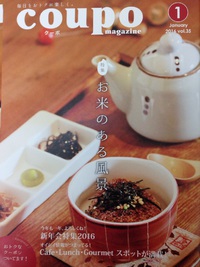2013年11月19日
新米♪ でも気をつけるポイントは一緒です。

平安座島のパン屋さん「ブランジェリーカフェ ヤマシタ」さんへ、
日曜にお邪魔しました。
fbフレンドさんがアップしてた“ハリネズミ”タイプのパンが
すごく・・・
・・・すごく
・・・可愛くて♪
ありがたいことに日曜営業(月・火が定休なようです)ということで
ムスメを引き連れて、地図を検索してGo

居ました、ハリネズミ。
他にもいくつかをチョイスしてレジへ。。
オーナーさんも気さくな方で、なにやらすぐに話し込んでしまいました(笑)。
海を眺められる、風の心地良いオープンスペースもあり
コーヒーなども置いているので、今度はゆっくり行こうと思います。
おはようございます。
昨日辺りから、また少し気温が下がっていますね。
調子はいかがでしょうか?
今日は琉球新報コラム「南風」掲載の日♪
この季節になると、店頭のお米も新米の率が多くなっているでしょう。
ここで気をつけてほしいのが
“新米だから”という概念。
新米だから、虫がでない
新米だから、水は減らす
・・・等々。
新米でも保管の状況がよくなければ虫も出ますしカビもします。
新米でも、まずは目盛り通りの水加減で最初は炊飯してみてくださいと
お話します。
そんなお話のコラムです。
ただ、コラム内では書ききれなかったことも多かったので
逆バージョンで備考をブログへ綴ります(笑)
「新米でも気をつけるポイントは一緒です」
この季節になると、新米も多く出ていることと思いますが、
お話しておきたいのがお米の保存について。
「なんで米には賞味期限って書かれてないの」と思った方いませんか?
なぜ、お米にはないのか。
私自身、扱う側としてはあまり気にしたことがなかったというか、
そういう風に考えたことがなかったのですが、
お客様からふと尋ねられたときに
“そういう考え方もあるのか”と気づかされました。
お米は精米加工後に袋詰めされたものですが、
野菜と同じ農産物扱いになります。
なので、野菜に賞味(消費)期限が表示されていないのと同じように
お米にもついていないのですが、そのかわり、お米には
「精米年月日」をつけることが決まっています。
考えてみてほしいのは賞味(消費)期限のない野菜でも、
そのまま置いておけば傷んでしまいます。
お米は穀物なので、水分量が野菜にくらべると少ないので長持ちしますが、
そのままにしておけば、やはりおいしさは低下してしまいます。
1番の理由としては、やはり「保管してある状況で、期限が全く異なるため」。
気温が高いと虫の発生率は高くなり、湿度が高いとカビの原因になったりします。
また、洗剤等のニオイの強いものの近くだとそのニオイが移ることもあります。
覚えててほしいのはお米の置いてある状況で、美味しさや品質が異なるということ。
野菜や生鮮食品であれば、記載されていなくても下ごしらえなどを行って、
冷蔵庫や冷凍庫に入れたり新聞にくるんで涼しい場所に置いたりするはずです。
もし、お米に賞味(消費)期限を記載するとします。
みんながみんな、同じ保管方法をするでしょうか?
きっと、みなさん方法は異なると思います。
なので、精米した日から約2~3週間で食べきれるくらいの量で
購入してほしいということになります。
お米だけが特別ではなくて、お米も食品です。
素麺やパスタ、しいたけや、かつお節も場所を考えないとカビちゃうし、
と思うはずです。
考え方としては一緒です。
農家が一生懸命育てたもの、私達はおいしく頂く責任があると考えています。
そう、食物を口にすることとは「きちんと食べるという責任」
それを教えることも食育ではないでしょうか。
こちらの過去記事も参考になるかと思いますので
合わせてご覧くださいませ♪
▼ ▼ ▼
ちなみに、最初の方で
“新米でも、まずは目盛り通りの水加減で最初は炊飯してみてくださいと
お話します”と書いています。
保管技術が進歩し、低温保管がほぼ当たり前のような環境になった今。
お米自体の劣化に関しては昔と比べて少なくなってきたと思います。
農家さんが稲を刈り、どのような乾燥をしたかで
実はその結果は変わってくるのですが、ふだん購入するものなどに
関しては、まず「目盛り通り」の水加減でトライしてみてください。
その様子をみて、水を減らすかどうかを検討しても良いと思います。
ただ、農家さんが機械での乾燥ではなく
架け干しと呼ばれるような、自然の状態での乾燥方法をした場合、
良い状態で乾燥ができれば、みずみずしいお米ができあがり、
そういうお米であれば水を減らさなくてはいけなくなったり、
逆に乾燥させ過ぎて割れやすくなっていたりなどがある場合もあるので
専門的な判断が必要なときもあります。
機械による乾燥の場合には、水分量を設定して行うことができるので
ほぼ均一な状態で仕上がるものです。
その均一な状態で仕上がったお米を
低温貯蔵で年間を通して保管することで
お米の劣化を防ぐことに繋がっているので
今のお米は大きな水分調節などが必要ないといわれているのです。
逆に・・・温保管ができなければ
呼吸をする玄米、どんどん水分を蒸発させてしまい
糠部分が酸化していくことで
パサついたり、ニオイが出たり
虫が発生しやすくなったりということになっていたのです。
それでも
いろんな技術が進歩したとしても
私達は「新米」というものに対しての想いは
格別なものがありますよね。
今日の琉球新報コラム「南風」も、こめななワールドお届けしております。
▼ ▼ ▼
「新米でも 気をつけるポイントは一緒」
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。