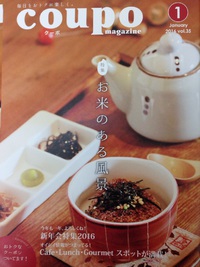2013年11月02日
舌の記憶

「健康、強靭な肉体を作る
心と体と魂をピカピカに!」
というコンセプトのもとに
ありがたやご主人のカフェ、11月7日に
オープンを予定しているカフェ♪


しっとりとした落ち着いた雰囲気の外人住宅カフェ。
日程はまだ未定ではありますが
ありがたやさんのご好意で、こちらで講座をさせていただくことに
なりました。
「“おいしい”を楽しむ」が私のコンセプト(笑)。
決まりましたら、お知らせします。
よろしくお願いします♪
おはようございます♪
朝方までは小雨が落ちていたのですが、綺麗な青空が広がっています。
こめなな・・晴れオンナになれそうです(笑)。
今日は、部活を引退したはずのムスメは
「大会があるから」とさっさと出かけてしまいました。
1年生と2・3年生が別になるそうで、2年生だけでは人数が足りないと
いうことで、引退組の出番だそうです。
ただね。
引退してからというもの、簿記に全く触れずにいたムスメは
職務を果たせるのでしょうか(▽//;)
気になる結果を心待ちにしておきましょう。。
そんなムスメ、朝は必ず「お米」を食べていきます。
私がお米を志す以前は、パンが主流だった記憶もあるのですが
いつの日か
「ごはんじゃないとお腹すく!」と子供達の方から
言ってくるようになりました。
最近、講座の打ち合わせなどで
「朝ごはん食べてこないこがいるんです。
子供だけでも作れるものってありませんか?」
朝にごはん(お米)以前に、
食べてこない、または食べてこられないコが多いのが
実情です。
そこでちょっとしたギャップがあるんですよね。
朝ごはんをたべましょう
↓ ↑
朝ごはんをたべない・食べられない
きっとそこが「食育」を進めていく上で
理想論と思われてしまうところ・・・
“食べよう”ということは、こめななブログでも何度か書いてきましたが
たぶん、その影響がどうあるのかを書いてなかったことと思います。
データで見る朝ごはんの大切さ
「よく体を動かし、よく食べ、よく眠る」という、成長期の子どもにとって
必要不可欠である生活習慣の乱れ。
文部科学省では生活習慣の乱れは、学習意欲や体力、気力の低下要因の一つとし、
平成18年4月から「早寝早起き朝ごはん」全国協議会を発足しました。
PTAをはじめ、経済界、メディア、有識者、市民活動団体、
教育・スポーツ・文化関係団体、読書・食育推進団体、行政など、
幅広い関係団体の参加を得て、「早寝早起き朝ごはん」運動を推進しています。
また、同年度から「子どもの生活リズム向上プロジェクト」として、
全国的な普及啓発活動や先進的な実践活動などの調査研究を行っています。
「全国学力・学習状況調査」では朝食をしっかりとっている子供ほど、
学業成績が良い傾向にあり、朝食を必ずとる子どもはほとんどとらない子どもよりも、
どの科目でも約2割も成績がよいいという結果が、実は出ているのです。
朝食と学力の関係については、
女子栄養大学副学長・栄養科学研究所長の香川教授も
「朝から集中して学習できる子を育てるためには、しっかりと朝食を食べ、
脳にエネルギー源のブドウ糖を送ることが重要である」としています。
また、「脳はブドウ糖しかエネルギー源として使うことが出来ないが、
肝臓がグリコーゲンとして蓄えているブドウ糖は僅か半日で消費されているため、
朝の脳にはブドウ糖が不足の状態である」とも。。。
▼ベネッセコーポレーション
第7回朝ごはんは学力を上げる?
もちろん、栄養バランスは考えてほしいところですが
まずは「食べる」習慣を持ちたいものです。
生活習慣の形成
子供はオトナの真似をします。
それが親であれば、何の疑いもなく真似るでしょう。
体のまだできていない子供達に
オトナと同じことでいいのでしょうか?
みなさんの思い出にある「おいしかったもの」、
思い出せますか?
いろんな方に同じような質問をよくするのですが(笑)
たいていオトナの方は子供の頃や若かりし頃に食したものを
語り始めます。
そして
その思い出す風景の中には
親しい人や家族が一緒に出てくるものがほとんどです。
大切な人や家族との思い出の中に必ず
「あれ、おいしかったね~」と出てくる記憶は
歳月が経ってもよみがえる記憶です。
舌に残る記憶は、同時にそんなあたたかい気持ちも
蘇らせてくれるもの。
そして
“頑張ろ”と思わせてくれるものだと私は思います。
まずは食べる・・から初めてみませんか?
いろんなことを気にするのは
きっとそこがスタートになれるはずですよ

Posted by こめなな at 10:10│Comments(0)
│食育
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。